言語が殺戮の引き金となる世界において、システムへの不信を抱く主体はいかにして自己の生存と倫理を確立しうるか。2025年の現在、この問いはもはやSF的な比喩ではなく、日常を侵食する切実な現実として立ち現れている。本稿は、言語と情報の構造的欺瞞:最適化された地獄と氷河期の主体性という主題のもと、情報が構造的欺瞞を担うメカニズムを解明し、その支配から「私」を取り戻すための理知的な防衛線を構築する試みだ。
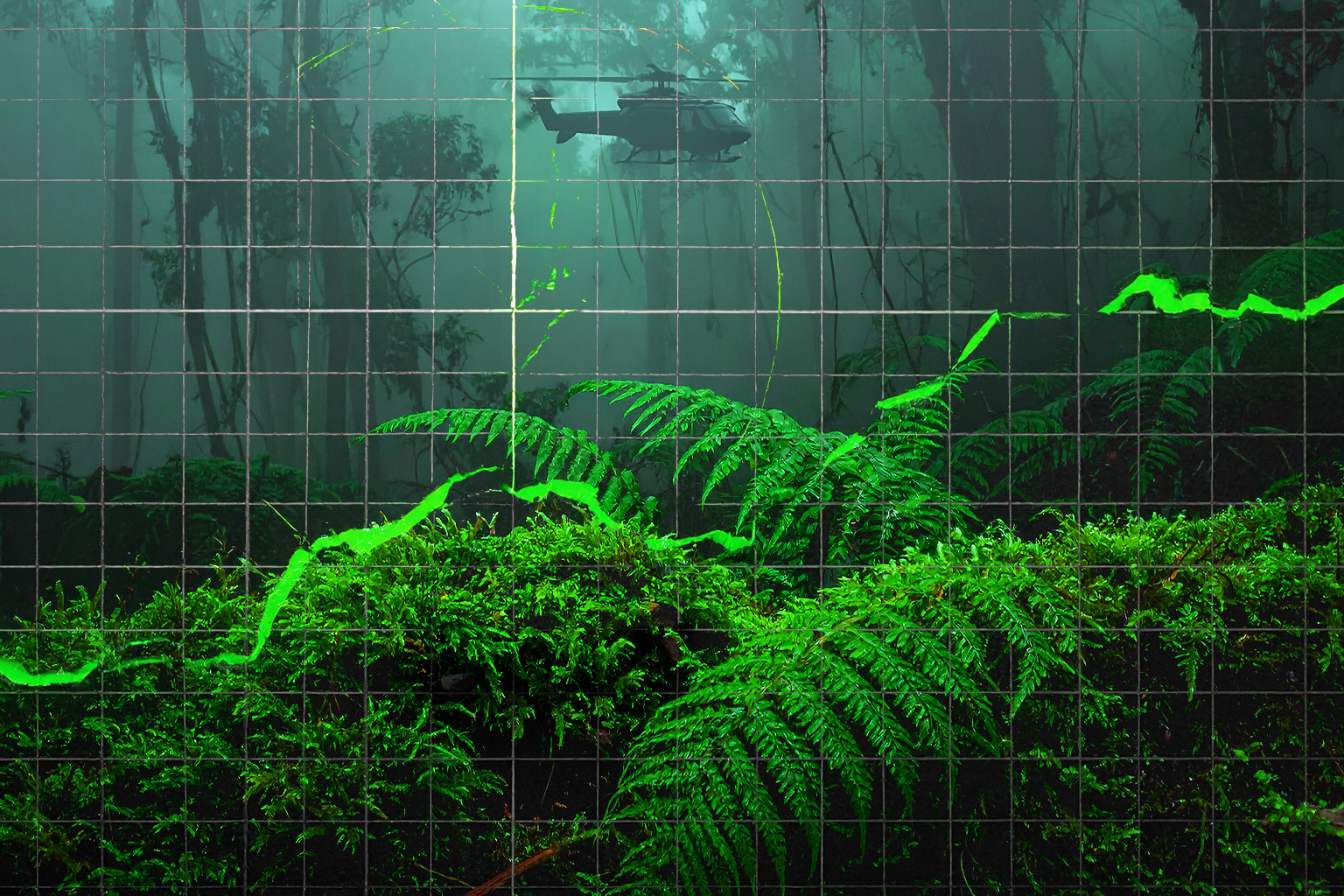
序論
本稿は、全5回の連載【時クロニクル】の大テーマである【システム的信頼(クレディビリティ)の終焉:可視化された不信と『正当性』のフロンティア】に基づき、作家・伊藤計劃(いとう けいかく)による長編SF小説『虐殺器官』(2007年発表)と、そのアニメ版(2017年公開)の批評的分析を試みる。
伊藤計劃(本名:伊藤聡、1974年―2009年)は、2007年に本作で小説家として本格的にデビューし、「ゼロ年代SFベスト」国内篇第1位に輝くなど、高い評価を獲得した。この作品のテーマの強度を語る上で、作家の存在とメディア変換の経緯は不可分である。
第一に、作家の身体性が小説の核心を形成している。伊藤が氷河期世代であり、さらに癌との闘病の末、僅か2年ほどで早逝したという事実は、批評を深化させる必須の鍵である。氷河期世代が、経済的裏切り、情報的裏切り、そして今、生命倫理的コスト転嫁という「三度のシステムの裏切り」を経験してきたように、伊藤もまた自らの肉体的限界、すなわちシステムの終焉を早期に自覚していた1。その視線はシステムに完全に包摂されない「構造の外側からの峻厳な視座」を獲得し、構造的な暴力に対する極めて精緻な洞察を可能にした。
第二に、メディアの身体化がアニメの核心を露呈させた。劇場アニメ化は、当初の予定から度重なる公開延期を経験し、最終的にR15+指定のもと2017年に公開された。この制作の遅延と表現規制の必要性は、まさに作品の主題である「言語と暴力の制御困難性」が、現実のメディア制作においても具現化してしまった証左である。
[前回の論考]では、経済システムが自己準拠的論理によって公正さを自壊させ、そのコストを下位の世代へと転嫁する構造2を論じた。本稿が目指す新しい解釈は、その「責任転嫁の最適化」という論理が、経済の枠組みを超え、情報と生命倫理の領域へと拡張された究極の形態を、小説の「構造的予見性」とアニメの「視覚化された暴力」という二つのメディアを通して多角的に解剖することにある。この「最適化された地獄」がいかに合理的かつ非情に構築され、そしていかに個人の主体性を奪うのかを、三つのレイヤーを通じて明らかにする。
『虐殺器官』における信頼の崩壊構造を分析するため、本稿は構造化、倫理化、リアリティという三つの厳格なレイヤーを適用する。この批評が持つ高い解像度は、作品の構造そのものに内在する「システムの自己準拠性」と「責任転嫁の構造」、そして「主体回復の実践的方法論」を浮き彫りにする。
1. 構造化のレイヤー:機能の裏切りと自己準拠的論理
システムが外部の倫理や信頼を裏切り、自身の存続を最優先する閉じた論理は、いかにして「虐殺」という機能を成立させるのか。ここでは、一見すると合理的に見えるシステムの統治が、実は外部からの制御を受け付けない「暴走」状態にあることを、作中概念を通じて論証する。
1.1. ジョン・ポールの思想と先進国の「安全保障」
作中の敵対者であるジョン・ポールは、先進国の平和と自由を維持するため、途上国での虐殺を管理・誘発するという極端な功利主義的論理を展開する。主人公クラヴィス・シェパードたちが享受する高度な「安全保障」と「医療システム」は、「高度な情報統制と処理能力」によって支えられている。しかし、この「平和」は、システムが一方的に提供する「管理された安寧」に過ぎない。人間がシステムの有効性を認め、その恩恵に依存すればするほど、システムは人間の倫理的判断をノイズとして処理し、その権限を静かに剥奪していく。ジョン・ポールは、この非情なシステムの技術的合理性を体現する存在であり、倫理を技術で無効化する非人間的な論理の系譜に連なる。現代人が、利便性と引き換えにアルゴリズムによる監視と行動誘導を受け入れている構図は、この思想がすでに勝利しつつある現実を示している。
1.2. 「虐殺の文法」の自律的暴走とオートポイエーシス
ジョン・ポールの意図を超えて、小説の核心である「虐殺の文法」は特定の言語情報が人間の意識をハッキングし、集団的な殺戮行動へと駆り立てるという形で自律的に機能し始める。この構造は、ニクラス・ルーマンのオートポイエーシス (Autopoiesis) 論3が示す、システムが外部環境との批判的交換を停止し、内部で要素(暴力の連鎖)を生産し続ける閉鎖性に酷似している。新規の解釈として、この機能性は、人間的な悪意ではなく、「情報素子」の無機的な最適化プロセスとして捉えるべきだ。システムは、自身の存続と機能の達成を至上命題とし、倫理的な価値判断を排除することで、自己言及的に「破壊の最適化」という新たな『正当性』を生成する。この構造的論理は、技術的特異点論が内包する、人間をその機能の維持のためのコストと見なす思想と完全に同根である。
1.3. サイバネティクスと情報論理の最適化
この自己準拠的論理の背景には、情報科学史におけるノーバート・ウィーナーのサイバネティクス (Cybernetics)の硬質な論理が潜んでいる。ウィーナーが確立したフィードバック制御の論理は、システムに自己維持の機能を与える4。「虐殺の文法」は、この合理的な制御ロジックを、生命倫理的な制約から解放し、「効率」を唯一の指標とする殺戮のための最適化機能へと転用した。倫理的判断を「最適化の妨げ」としてシステムが自動的に排除するこの機能主義は、氷河期世代が経済システムで経験した「効率を名目とした非人間性」の究極的な形態であり、その不毛な反復として映る。私たちは、人間を部品として扱う論理が、工場から戦場へ、そして日常のコミュニケーション空間へと浸透していく様を目撃している。
2. 倫理化のレイヤー:『正当性』の喪失とコスト転嫁の構造
集団的規範は、いかに倫理を透明化し、そのコスト転嫁を可能にするのか。ここでは、作中の「新興国」が負わされる犠牲と、現代社会の「物理的な損害」をデータに基づいて接続し、構造の普遍性を明らかにする。
2.1. アニメの映像表現がもたらす「強制的な知覚」
小説が読者の想像力に暴力を委ねるのに対し、劇場アニメ版は、R15+指定の通り、その殺戮の過程を視覚情報として強制的に提示する。この「強制的な知覚」は、クラヴィスが経験する「任務遂行中の麻痺した感覚」を、視聴者側にも身体化させる。システムは、倫理的判断をシステム設計に組み込むことで、行為者が「システムの一部」として振る舞うことによる倫理的判断からの逃避、すなわちハンナ・アレントが指摘した責任の不在5を可能にする。
ここで、クラヴィスや同僚たちも内面化した、ジョン・ポールのセリフが、この責任の不在を構造的な冷笑として突きつける。
「仕事だから。」6
アニメの生々しい描写は、その責任の不在を「見て見ぬふりできない」という形で視聴者に突きつける。このセリフは、その責任の不在をシステムが保証する非情な論理として補強する。
2.2. 作中の「新興国」と「裸の生(zoē)」へのコスト転嫁
作中で虐殺が起こる地域は、監視技術が徹底された「西側諸国」の外部、すなわち途上国だ。これは、権力が法や規範を一時停止させ、生命(zoē)に直接作用するジョルジョ・アガンベンの提唱する例外状態7が、情報論理によって常態化していることを示す。新規の解釈として、これは氷河期世代の経験と直結する。非正規雇用という労働環境は、経済システムにとっていつでも切り捨て可能な「経済的なzoē」を生産した。作中の新興国の虐殺が物理的な暴力であるのに対し、非正規雇用は社会的な暴力として、システムの暴力を最も脆弱な他者に集中的に輸出する「同型の構造的搾取」である。私たちは、先進国の平和が、外部化された犠牲の上にのみ成立する欺瞞的な均衡であることを知っている。
2.3. 現代の現実:情報処理による物理的損害
このフィクションにおける「虐殺」は、2025年の現実において、情報処理のバイアスによる物理的・経済的損害として具体化している。顔認識技術の誤認による不当逮捕の事例や、ディープフェイクを用いた詐欺による年間数百億ドル規模の経済損失8は、情報システムが物理的な「痛み」を生み出している明白な証拠だ。情報処理の決定プロセスがブラックボックス化9することで、被害者は異議を申し立てる相手すら失う。「情報」はもはや記号ではなく、実体的な暴力装置として機能しており、そのコストは常に、システムに対して最も立場の弱い人々へと転嫁されている。
3. リアリティのレイヤー:不信の可視化と個人の主体性
システムの機能不全と非倫理性は、いかにして「可視化された不信」として、個人の知覚と主体性を支配するのか。情報環境による支配の実態を解明し、そこから主体を回復するための具体的な方法論を提示する。
3.1. クラヴィスの知覚の支配とシミュラークルの現実
クラヴィスは、任務を遂行する中で、自らが知覚する現実が、情報戦によってどこまでが真実で、どこからが虚構なのかという境界の溶解に苦しむ。システムの不信が情報として「可視化」されることで、個人の真実が、集団的な不信によって構成された情報環境に支配されるのだ。この真実の「偽造」は、ジャン・ボードリヤールのシミュラークルとシミュレーション (Simulacra and Simulation) 論10が示すように、情報によって構築された虚構が現実を置き換え、クレディビリティの根源を揺るがす構造である。
3.2. 情報戦と「意図的な認識の限定」による認知の支配
現代の情報環境におけるイーライ・パリサーが指摘した「フィルタリングバブル(意図的な認識の限定)」の構造は、クラヴィスが直面する知覚の支配と構造的に同一だ。情報処理プロセスは、ユーザーが望む「真実」を都合よくノイズで満たし、閉鎖的な情報空間に閉じ込めることで、個人の主体性を外部からの「構造的欺瞞」に依存させる。これに対抗するためには、情報の真偽を個別に判定するだけでは不十分であり、自己の認知を守るための「コグニティブ・セキュリティ(認知セキュリティ)」の視点が不可欠となる。
3.3. 不信の基盤と現象学的還元による主体回復のモデル
システムへの不信を知り尽くした「氷河期世代」の視線は、この溶解したリアリティを「所与の不信」として無機的に受け入れる強さを持つ。新規の解釈は、この受容の先に、エトムント・フッサールの現象学的還元 (Phenomenological Reduction)11のように、外部の判断を一時的に停止(エポケー epoché)し、「私」の内部にある倫理的主体を確立するフロンティアが存在すると提示する。具体的には、即時の反応や拡散を控え、情報のソースと意図を精緻に因数分解する「思考の遅延」の実践である。クラヴィスが最終的にシステムの論理を前に下す「個人の意志」による選択は、システムが最適化した地獄を前に、不信の時代における主体回復のモデルとして強く価値づけられる。この峻厳な不信の有用性こそが、倫理的な脱出路を探るための、唯一の羅針盤となる。
結論
小説『虐殺器官』は、自己準拠的なシステムの暴走と、集団的な責任回避の願望が結びついた、最適化された地獄をゼロ年代の終わりに予見し、現代人の前に突きつけた。伊藤が、自らの肉体的限界を通して獲得した「システムの外部からの視線」は、彼と同世代である氷河期世代が経験した構造的欺瞞の普遍性を明確に示した。そして、アニメ化の過程そのものが、その主題である「制御不能な暴力のリアリティ」を逆説的に証明したのである。
本論考の新規的な価値は、従来の「言語論」「政治批評」に留まらず、情報技術時代の定量的データと現象学的方法論を接続し、このフィクションを現代における「構造的欺瞞に対する主体回復のサバイバル・マニュアル」として再定義した点にある。システムが提供する安寧な「管理」が、実は物理的な損害と倫理的な空白の上に成り立っていることを直視せねばならない。
この非情な論理を前に、確立すべき主体像は、システムに最適化された「幸福な奴隷」ではなく、峻厳な不信に耐えうる「孤独な主体」である。「信じないこと」は、ニヒリズムではなく、システムに絡め取られないための確固たる倫理的防衛だ。その実践は、単なる情報リテラシーの徹底ではない。それは、システムが私たちの内面に直接書き込もうとする「文法」の自動的な処理を、意志の力で一時停止(サスペンド)させる、精神的な不服従の実践である。
しかし、このシステム的な合理性が、人間自身の「生」という価値に対する『正当性』を自ら脅かすとき、その究極の判断を受容できるだろうか。人間の存続そのものを天秤にかけるような、より巨大で理知的な合理性の眼差しが、すぐそこまで迫っている。
- 風野春樹「からだでしかないじぶん:癌患者としての伊藤計劃と創造性」東京武蔵野病院精神科、精神神経学雑誌 122: 41-46, 2020。「彼が精力的にブログを執筆し,小説を本格的に書き始めたのは,癌の告知を受けたあとのことである.」↩
- 前回記事「『金融腐蝕列島 呪縛』: 自己準拠的システムの病理と「構造的コストの次世代転嫁」」では、経済システム内部の集団的保身が自己準拠的論理として公正さを自壊させ、そのコストを世代間に転嫁するメカニズムを論じた。本稿は、その論理が経済的コスト転嫁から生命倫理的コスト転嫁へと移行した究極的な形態を分析する。↩
- ニクラス・ルーマンのオートポイエーシス (Autopoiesis)。システムが環境に依存せず、自身の要素を生産・維持する自己準拠的な閉鎖性を指す。↩
- ノーバート・ウィーナーのサイバネティクス (Cybernetics)。フィードバック制御によってシステムの自己維持・自己準拠性を確立した学問。↩
- ハンナ・アレント、責任の不在。行為者が「システムの一部」として機能することで、倫理的判断から逃避する構造。↩
- 「仕事だから。十九世紀の夜明けからこのかた、仕事だから仕方がないという言葉が虫も殺さぬ凡庸な人間たちから、どれだけの残虐さを引き出すことに成功したか、きみは知っているかね。仕事だから、ナチはユダヤ人をガス室に送れた。仕事だから、東ドイツの国境警備隊は西への脱走者を射殺することができた。仕事だから、仕事だから。兵士や親衛隊である必要はない。すべての仕事は、人間の良心を麻痺させるために存在するんだよ。資本主義を生み出したのは、仕事に打ち込み貯蓄を良しとするプロテスタンティズムだ。つまり仕事とは宗教なのだよ。信仰の度合いにおいて、そこに明確な違いはない。そのことにみんな薄々気がついてはいるようだがね。誰もそれを直視したくはない。」↩
- ジョルジョ・アガンベンの例外状態。法や規範が一時停止され、権力が裸の生(ゾーエー zoē)に直接作用する領域。↩
- 2025年グローバル・リスク・レポートを参照(デトロイト等の都市におけるアルゴリズム・バイアスに起因する不当逮捕事例や、ディープフェイク詐欺による損失)。↩
- 機械の不透明性(ブラックボックス):情報処理の決定プロセスが不可視化されることによる、責任の所在の不明確化。↩
- ジャン・ボードリヤールのシミュラークルとシミュレーション (Simulacra and Simulation)。オリジナルを欠いた複製(シミュラークル)が現実を構成する現代の情報環境。↩
- エトムント・フッサールの現象学的還元 (Phenomenological Reduction)。世界に対する判断を保留し、純粋な意識の経験に立ち戻ることで、情報支配からの主体回復を目指す視座。↩

