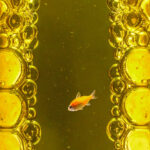情報の自動生成が飽和し、最適化された静寂が支配する2026年の冬、私たちは再びあの血の匂いと鉄の軋みに回帰しなければならない。あらゆるノイズが「不快なエラー」として除去され、アルゴリズムが差し出す清潔な幸福に浸りきった私たちの肉体は、今やシステムの末端で静かに拍動を刻むだけの演算資源へと成り下がっている。
この去勢された現代の静寂を切り裂くのは、1997年のスクリーンから放たれた、あの剥き出しの咆哮だ。シシ神の森で流される鮮血、タタラ場の鞴(ふいご)が吐き出す熱気、そしてタタリ神の蠢きが放つ管理不能なテクスチャ。それらは、かつて私たちが「生きる」という言葉に託していた、飼い慣らされない、能動的で、美的な生命力の記録である。
本稿では、黒曜石の贈与に秘められた「呪いの等価交換」を糸口に、和解なき世界で地べたを這い、自律した知を持って生き抜くための「再野生化」の戦術を解体する。

序論:神なき荒野での再野生化
本稿は、全5回にわたる連載企画【「脱出」としての倫理:計算と制約の外部へ向かう「自律的な生の野生」の起動】の第2回である。[前回の論考]では、情報の解体による勝利を描いた。そこでは、非論理的なコードが、演算のみで構成されたシステムの外部を切り拓く様を追った1。だが、システムを破壊した後に広がるのは、約束されたユートピアではない。
2026年の現在、私たちはAIという新たな神が統べる管理社会に生きている。ここでは、あらゆるリスクが予測モデルによって事前に排除され、失敗の可能性すら奪われた「清潔なディストピア」が完成しつつある。この窒息しそうな安全圏の中で、『もののけ姫』を観直す意義はどこにあるのか。それは、神を殺した後の荒野において、剥き出しの肉体がいかにして自律した知2を駆動させ、共生へと至るかというシミュレーションを行うためである。本作が描くのは、環境保護の綺麗事ではない。聖域を自らの手で汚し、その泥の中で生きる覚悟を決めるための、残酷な通過儀礼である。
1. 聖域の脱地平と技術的遊牧民の叛逆
本章では、網野善彦の中世史観と現代のプラットフォーム労働を接続し、タタラ場という職能集団が持っていた「無縁」の力学を解明する。
1.1. 網野史学の再起動と現代のギグワーク
網野善彦は、農耕民族という均質な日本人像を解体し、山民や職能民といった「非農業民」3が持っていた自由を明らかにした。彼の史観は、土地に縛られる定住者(=システムに従属する者)と、道を移動し技術を操る遍歴者(=システムを横断する者)の対立と交流を浮き彫りにする。
この視座は、2026年の労働環境において極めて批評的な意味を持つ。私たちは今、ユニバーサル・ベーシック・コンピュート(UBC)やAIによる最適化によって、生存を保障される代わりに「思考の自由」を譲り渡した、デジタルの小作農となりつつある。一見、フリーランスやギグワーカーは自由に見えるが、その実態は巨大プラットフォームのアルゴリズムに管理された、現代の隷属民に過ぎない。
対して、エボシ御前が率いるタタラ場を見よ。そこに集う元娼婦や癩者(ハンセン病患者)たちは、既存の共同体から「死んだ者」として切り離された人々である。しかし彼らは、被害者として憐れみを乞うことはない。彼女たちが足を踏み鳴らし、灼熱の鞴(ふいご)を吹くとき、その身体は汗と煤にまみれ、圧倒的な「生の熱量」を発散している。これは単なる労働描写ではない。社会的な死を宣告された者が、製鉄という高度な技術(=システム)を自らの手で掌握し、支配者層(侍や地侍)に対抗できる力を獲得する、叛逆のプロセスである。
ここで想定される反論がある。「タタラ場の労働もまた、エボシというカリスマによる搾取ではないか」という批判だ。現代のブラック企業と何が違うのか、と。だが、その批判は決定的な点を見落としている。タタラ場の女たちは、エボシに対して敬語を使わず、対等に口をきく。そこにあるのは、契約や恐怖による支配ではなく、共に「鉄」という価値を生み出し、運命を切り開くという共犯関係による連帯だ。彼女たちの「自律」は、システムに飼われることへの拒絶から生まれている。現代の私たちが失ったのは、この「自分たちのルールを自分たちで作る」という、技術的遊牧民としての気概ではないか。
1.2. 宇宙技芸としての神殺し
ユク・ホイが提唱した宇宙技芸4の視点に基づけば、エボシ御前が行ったことは、地域特有の神話的秩序を「技術」という普遍的理性によって上書きする行為である。
かつてシシ神の森は、「入ってはならない聖域」という宇宙論によって守られていた。それは人間にとっての不可侵領域(ブラックボックス)であり、畏怖の対象であった。しかしエボシ御前は、石火矢というテクノロジーを持ち込むことで、そのブラックボックスを強制的にこじ開けた。彼女にとって森は、もはや神の住処ではなく、木炭と砂鉄という「資源」の集積地に過ぎない。
これは、2026年の私たちが直面している「世界のデータ化」と完全に重なる。AIとセンサー技術は、あらゆる場所、あらゆる行動、あらゆる感情をデータセットとして解析し、世界の「神秘」や「不可解さ」を剥ぎ取っていく。エボシが森を焼く炎は、現代のデータセンターが排出する熱そのものだ。私たちは、世界を「計算可能な対象」へと世俗化させるプロセス(Planetary Realism)の只中にいる。
しかし、エボシの行動を単なる環境破壊として断罪するのは早計だ。彼女が神を殺そうとしたのは、支配欲からではない。シシ神(自然の摂理)が黙認していた「業病は前世の報いである」という理不尽な運命論、そして「女は汚れている」という当時の社会通念を破壊するためだった。彼女は、神に守られる客体であることを辞め、自らの手で世界を構築(テラフォーミング)する主体となるために、あえて神殺しという大罪を背負ったのだ。サイバーセキュリティの文脈で言えば、彼女は「神」という名の管理者権限(Root)を、物理的な攻撃によって奪取しようとしたハッカーである。
1.3. 加速主義的救済の限界
エボシ御前の合理主義は、不完全な人間を包摂するために神を殺すという加速主義5的な側面を持つ。彼女は「古い森」を犠牲にし、「新しい国」を作ろうとした。
しかし、宮崎駿が描く結末は、エボシの完全勝利を許さない。シシ神の首を飛ばした後、世界はどうなったか。そこには約束された繁栄ではなく、粘菌のようなドロドロとした死の物質が溢れ出し、敵も味方も等しく飲み込んでいくカオスが出現した。これは「神なき最適化」が招く、制御不能な副作用のメタファーである。
ここで注目すべきは、4Kリマスターによって鮮明になった、その死の物質やタタリ神が放つ「肉体のテクスチャ」だ。 1997年、ジブリが初導入したCG技術が託されたのは、滑らかな動画ではなく、生理的な不快感を伴う「管理不能な蠢き」であった。現代のAIが「清潔な画像」を自動生成するのに対し、本作のデジタルは、手描きの野生を汚染し、制御不能に暴走させる「呪いの視覚化」として機能している。
エボシの加速主義的救済――すなわち理性的管理――は、このドロドロとした、計算不可能な「肉体のノイズ」によってあえなく瓦解する。現代社会において、私たちはテクノロジーによる解決を無邪気に信じすぎているが、『もののけ姫』は冷徹に告げる。神(絶対的な外部)を殺した代償として、人間は剥き出しのエントロピー増大、すなわち「制御不能なテクスチャの渦」の中に放り出されるのだ、と。
シシ神の死後、森には「ただの風」が吹くようになる。それは、もはや人間を罰しもしなければ、守りもしない。意味を剥奪された、空虚で即物的な空間。この「神話の後の虚無」こそが、2026年の私たちが立つ現在地である。救済が死に、理性が敗北したこの地べたからしか、真の「呪いの等価交換」も「再野生化」も始まらないのだ。
2. 黒曜石の贈与と欠損のプロトコル
本章では、新実在論の観点からアシタカの行動を分析し、4Kリマスター化によって強調された物理的テクスチャがもたらす身体的変容を論じる。
2.1. 黒曜石という断絶のインターフェース
物語序盤、アシタカが許嫁のカヤから受け取った黒曜石の小刀。彼はそれを、物語の中盤でサンに譲り渡す。この行為は、公開当時から現在に至るまで、「元カノのプレゼントを今カノにあげる不誠実さ」として、ネット上で度々揶揄されてきた。現代の恋愛規範や所有の概念からすれば、確かにアシタカの行動は不可解に見える。
しかし、これをマルクス・ガブリエルの新実在論的な文脈6で読み解けば、まったく別の地平が見えてくる。アシタカにとって、カヤの小刀は「エミシの村」という意味の場(=人間中心の古い秩序と愛)の象徴である。一方、サンは人間を憎み、言葉の通じない「もののけ」の意味の場に生きている。この二つの断絶された世界を接続するためには、言葉や論理といった上位レイヤーのプロトコルは機能しない。
必要なのは、自らのアイデンティティの核となっている「最も大切なもの」を、物理的なオブジェクトとして外部化し、相手の懐にねじ込むという荒技だ。アシタカは、カヤへの愛を軽んじたのではない。むしろ、その愛が凝縮された小刀を「触媒」として差し出すことでしか、サンという完全な他者と接続できないと直感したのだ。これは「過去の自分(村の英雄)」を殺し、「呪われた身体」のまま境界を生きるという宣言に他ならない。
現代のSNS空間では、私たちは「いいね」やスタンプという、コストのかからない記号の交換だけで関係を済ませようとする。だが、アシタカの贈与は痛みを伴う。黒曜石は鋭く、触れれば指が切れるガラス質の石だ。この「呪われたギフト」こそが、異なるOSを持つ者同士が共生を開始するための、唯一の実効性ある通信プロトコルとなる。「大切にする」とは、タンスにしまっておくことではない。最も決定的な局面で、それを手放すことなのだ。
2.2. 肉体のノイズと音響の物理学
4Kデジタルリマスター化、及び2025年の久石譲シンフォニック・コンサートにおける音響再検証は、本作の聴覚的体験を劇的に更新した。特に注目すべきは、サンの叫びやアシタカの呻きに付与された、デジタル代替不能な「喉の震え」である。
高解像度の音響システムの下では、石田ゆり子(サン)の声に含まれる、微細なノイズが前景化する。彼女の演技について、かつては「棒読み」という批判もあった。しかし、AIによる合成音声が完璧なイントネーションで喋り続ける2026年にあって、彼女の声の「揺らぎ」や「不器用さ」は、圧倒的なリアリティとして響く。それは、文明社会の言語体系に飼い慣らされていない、獣の警戒心と純粋さが宿った「野生の音」だ。
映像においても同様だ。4K化によって暴き出されたのは、美しい背景美術だけではない。泥にまみれたアシタカの頬、血の乾いたサンの口元、エボシの着物の重たい衣擦れ。これらの「テクスチャ(質感)」は、観客の皮膚感覚に直接訴えかける。平滑なディスプレイの中で、記号として消費されるアニメーションとは異なり、ここには「触覚的な痛み」がある。
批評家は言うかもしれない。「映画館での身体感覚など、一過性の興奮に過ぎない」と。だが、システムがすべてを平準化しようとする時代において、この「一過性のノイズ」こそが重要だと私は反論する。観客の身体に刻まれた、弓を引き絞る際の軋むような感覚。その一瞬の戦慄(チル)は、論理的な解析をすり抜け、身体の深層にバグとして潜伏する。いつか日常のふとした瞬間に、そのバグが起動し、管理された世界への違和感として噴出する。それこそが、芸術が持つ遅効性の毒である。
2.3. 境界侵犯する身体の美学
スーザン・ネイピアは、サンを既存のジェンダーやヒエラルキーを無効化する境界侵犯者(Transgressor)7として位置づけた。
サンは、お姫様でもなければ、守られるべきヒロインでもない。かといって、単なる復讐の鬼でもない。彼女は口元を血で染めながら、母であるモロの君に甘え、アシタカに対しては警戒と好奇心の入り混じった複雑な視線を向ける。この流動的で矛盾に満ちた身体性は、個々人を「属性」や「カテゴリ」へ収納し、データベース化しようとする2026年の多様性論(アイデンティティ・ポリティクス)をあざ笑うかのように、分類不可能だ。
サンが体現するのは、「人間であること」さえも辞めた後に残る、原初的な生命力である。彼女の美しさは、化粧やファッションによる装飾ではない。生きるために走り、殺し、喰らうという、能動的な運動の中から立ち上がる「機能美」だ。私たちは「自分らしさ」という言葉に囚われすぎている。だがサンは教えてくれる。自己とは、守るべき核ではなく、他者(アシタカや森)と激しく衝突する瞬間にのみ発生する火花のようなものである、と。
3. 和解なき共生の設計図と地べたへの視線
本章では、レナ・デニスンの産業論を参照し、物語の結末が提示する「神なき荒野」での生存戦略を統合的に分析する。
3.1. ハイブリッド神話と生産のポリフォニー
レナ・デニスンは、本作を時代劇、ファンタジー、エコロジーといったジャンルが混交し、解体されたハイブリッドな産業物8として分析した。複数の制作意図、例えば宮崎の作家性、鈴木敏夫の商業戦略、網野善彦の歴史学、そして海外配給を担ったミラマックスの要請などが衝突して生まれたこの多声性(ポリフォニー)は、単一のメッセージへの集約を拒む。
「自然を大切に」というスローガンで本作を語ることは不可能だ。なぜなら、映画そのものが、鉄を作り自然を破壊するタタラ場の熱気をも肯定的に描いているからだ。この「どっちつかず」の曖昧さこそが、実は強靭な生存戦略となる。資本主義システムは、明確なメッセージを持つ作品(プロパガンダ)を簡単に消費し、飽きさせることができる。しかし、矛盾を孕んだまま回転し続ける『もののけ姫』という塊は、システムにとって消化不良を起こさせる「異物」であり続ける。
2026年の私たちは、SNSのタイムラインで日々行われる「正義の殴り合い」に疲弊している。白か黒か、敵か味方か。だが、本作が提示するのは、矛盾を矛盾のまま抱え込み、そのダイナミズムの中で物語を駆動させる知恵だ。回収されることを恐れず、むしろ巨大産業の中に「解決不能な問い」として居座り続けること。これこそが、現代におけるメディア戦略としての再野生化である。
3.2. 熱力学的静寂としてのシシ神の消滅
物語の結末、シシ神は首を取り戻しながらも朝日を浴びて消滅する。その後、ハゲ山には緑が戻るが、それはかつての鬱蒼とした原生林ではない。手入れのしやすい、若く平凡な緑である。
これを「自然が蘇ってよかった」と安堵するのは、あまりにナイーブだ。物理学的な視座に立てば、これはエントロピーが増大9し、特別な力が失われた後の「熱力学的な静寂」である。シシ神が生と死を自在に操れた「魔法の時代」は終わり、世界は物理法則だけが支配する不可逆な時間の中に投げ出された。
2026年の冬、私たちが感じる閉塞感は、このラストシーンの静けさと共振する。予測モデルがすべてを予見し、奇跡が起こり得ない世界。私たちは、魔法や神に頼ることなく、この「つまらない緑」の風景の中で生きていかなければならない。シシ神亡き後の自然は、もはや人間を癒やしも祟りもしない、ただそこに「ある」だけの即物的な物質だ。だが、その「意味のなさ」を受け入れたとき、初めて私たちは自然をロマンチックな幻想としてではなく、対等な他者として直視できるのではないか。
3.3. 欠損の受容と日常へのテラフォーミング
「共に生きよう。会いに行くよ」アシタカはタタラ場に残り、サンは森へ帰る。二人は決して一つにならず、それぞれの断絶を抱えたまま、別々の場所で生きることを選ぶ。
この「和解なき共生」10の結末において、アシタカの腕には呪いの痣が薄く残り、失われた身体機能や、破壊されたタタラ場は元には戻らない。ここにあるのは、喪失と欠損の全肯定だ。ハリウッド映画的な「完全な回復」や「ハッピーエンド」は拒絶される。
しかし、この「欠損」こそが、私たちが他者と出会うための通路となる。完全無欠な人間などいない。私たちは皆、何かを失い、傷を負い、システムに搾取されながら生きている。だからこそ、その凸凹を合わせるようにして誰かと関わることができる。タタラ場の再建は、かつての再現ではないだろう。エボシもまた片腕を失った。その欠損を抱えた身体で、彼女たちは新しい「良き村」を作ろうとする。それは、管理された日常という重力に対し、自らの手で生活圏をリノベーション(テラフォーミング)していく、静かだが力強い闘争の始まりである。
結論:傷跡という名の自律
神話を殺し、地べたに這いつくばるようにして歩き出した私たちの視線は、次に一人の「車椅子の少女」が潜む深海へと向けられる。それは、社会の周縁に押し込められた肉体が、虎や魚といった幻想的なイメージを借りて、いかにしてこの残酷な現実を上書きし、生存可能な場所へと変えていくかという、より切実でパーソナルな物語へと接続されていく。
次回、私たちは海辺の静寂の中で、社会の境界線と、そこから跳躍する意志の形を問うことになるだろう。そこには、もはや英雄ですらない、等身大の私たち自身の姿が待っている。
- 前回記事「『超時空要塞マクロス』:水浸しの擬似家庭と「野生」の起動」では、「歌」という非論理的なコードによる情報の解体と、演算システムのオーバーフローを「生の野生」の初期的発動として論じた。↩
- ここでいう「自律した知」とは、他者に飼い慣らされない、能動的で美的な生命力そのものを指す。縄文的な回帰ではなく、現代の技術環境下で再構築される野生である。↩
- 網野善彦は、山民・海民・職能民・漂泊民など、農耕を基盤とする身分秩序に組み込まれず、移動と技術を通じて社会を横断した人々を「非農業民」と総称した。彼は、定住農民中心の単一的な日本史像を相対化し、国家や共同体の枠外に広がる多様な自由領域こそが、日本社会の多元性を支える重要な構造要素であることを示した。網野善彦『日本社会の歴史』(上・中・下、岩波新書、1997年)。↩
- Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics, Urbanomic, 2016. 日本語訳:ユク・ホイ『中国における技術への問い――宇宙技芸試論』(伊勢康平訳、ゲンロン、2022年)。 技術を単なる道具としてではなく、特定の宇宙論(Cosmology)や道徳(Moral)と統合された営みとして再定義する概念。↩
- Nick Srnicek and Alex Williams, Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work, Verso, 2015. 現状の技術的・社会的プロセスを加速・過剰化させることで、既存の資本主義体制の限界を突破しようとする政治思想。↩
- Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, Ullstein Verlag, 2013. 日本語訳:マルクス・ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(清水一浩訳、講談社選書メチエ、2018年)。世界全体という包括的な枠組みは存在せず、無数の「意味の場」が重なり合って存在するという思想。↩
- Susan J. Napier, The Anime Art of Hayao Miyazaki, Palgrave Macmillan, 2018. サンを、人間/自然、男/女、善/悪といった二元論的境界を侵犯し、攪乱する存在として定義。↩
- Rayna Denison, Studio Ghibli: An Industrial History, Palgrave Macmillan, 2023. ジブリ作品が、国内の文脈とグローバルな市場戦略、作家性と商業性の間でいかにしてハイブリッドな価値を生成したかを分析。↩
- (エントロピー:熱力学第二法則に基づき、閉鎖系における無秩序さ(乱雑さ)が増大することを示す指標。ここでは、シシ神による「奇跡的な秩序(低エントロピー)」が失われ、物理法則のみが支配する「平凡な平衡状態(高エントロピー)」へ移行したことを指す。↩
- 宮崎駿は『もののけ姫』製作発表(1997年)において、人間と自然のあいだに「和解はない」と断言し、その断絶を抱えたまま生きる肯定を描く意図を表明している。この認識は、一貫している。宮崎駿『折り返し点 1997〜2008』(岩波書店、2008年)。↩