そのビデオテープは、単なる都市伝説ではなく、私たち自身の倫理的基盤を攻撃する機能不全システムの精巧なプロトタイプであった。ホラー映画の古典的名作として語られてきた中田秀夫の映画『リング』は、現在において、単なるメディア論の予見としてではなく、『正当性』の信頼(クレディビリティ)が根底から汚染されることとしてのシステム的信頼の終焉という課題を冷徹に映し出す構造分析の対象となる。ここでは、呪いのビデオというシステムを、外部の倫理や法に依存せず自己増殖する自己準拠的論理の完璧なモデルとして捉え直し、主人公たちの行為を、リスクとコストの外部化を強制する非倫理的システムロジックとして厳密に再解釈する。この再解釈は、現代のAIのブラックボックス化やネオリベラル的生存競争における責任の不可視化という、抽象度の高い現代思想的課題を、身体的な恐怖という具体的な描写と接続することで、課題の本質への理解を促す。では、この構造的破綻システムが、いかなる形で私たちの倫理的存続を脅かしているのか。
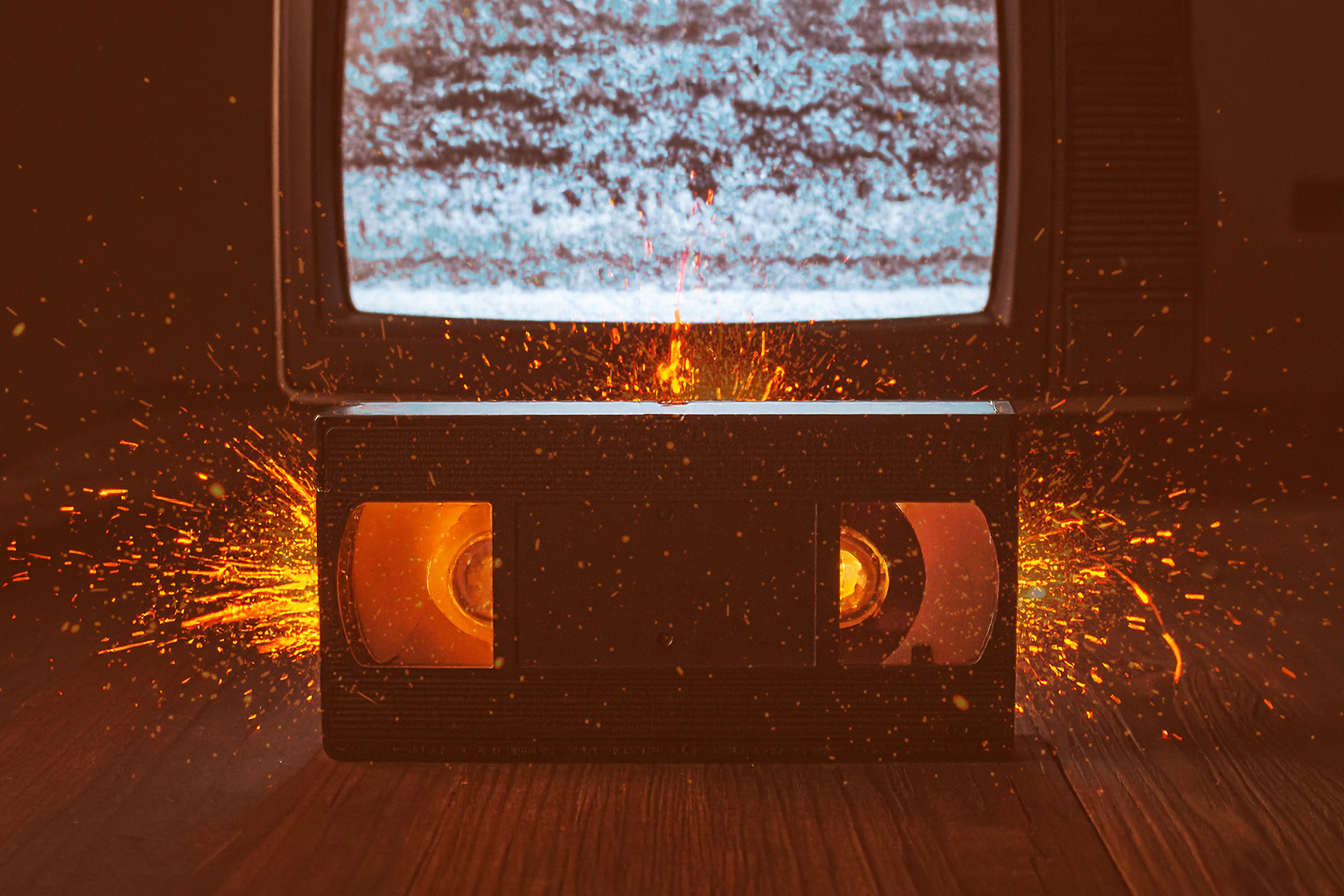
序論
本稿は、【システム的信頼(クレディビリティ)の終焉:可視化された不信と『正当性』のフロンティア】という大テーマに焦点を当てた全5回連載1の一部であり、[前回の論考]2が扱った受動的な共同幻想の規範から、より能動的で非人間的な感染の論理へと分析軸を移行させる。
分析の対象とするのは、鈴木光司によるミステリ・ホラー小説『リング』を原作とし、中田秀夫が監督を務め1998年に公開された映画『リング』である。小説版はその後も続編が刊行されており、映像化は、1995年と1999年のテレビドラマ、そして1998年の日本映画のほか、2002年のアメリカ映画『ザ・リング』や韓国映画など、国際的なメディアミックスが行われた。特に日本映画版は配給収入10億円を記録し、その後のJホラーブームの火付け役となった。この作品が発表された1990年代後半は、日本のバブル経済崩壊後、金融不安と終身雇用制度の揺らぎが顕在化し、従来の批評が指摘してきた日常に潜む恐怖や情報化社会の不信が、国民的な共感を得た背景である。
しかし、本稿の視座は、これらの従来の言説を土台としつつ、さらに構造的な次元へと切り込む。従来の解釈が怨念やメディアの媒介性に焦点を当てたのに対し、この物語に内在するシステム論理が、いかにして私たちの『正当性』の基盤を汚染し、リスクを他者へ転嫁することを強制する機能不全の原型であるかを考察する。特に、氷河期世代の冷徹な視線をもって、従来の議論を超え、システムの構造、その作用としての倫理の自壊、そして結果としてのリアリティの溶解という三つの次元で考察を行う。
1. 構造化のレイヤー:機能の裏切りと自己準拠的論理
システムが自己の存続を至上命令とするオートポイエーシスの論理は、外部の倫理を排除し、人間を単なる機能部品へと還元する。本章では、呪いのシステムがこの自己複製をいかに強制するかのメカニズムを、情報社会論の観点から解明する。
1.1. 技術的媒介性の変容:VHSからAIへのシステムの進化
呪いのシステムは、VHSテープという物理的なアナログ媒体から発動するが、その本質は拡散アルゴリズムである。従来のメディア論は、VHSの物理性に注目したが、本稿は、これが現代のAIによる自動的な増幅・拡散へと進化し、責任の所在を人間からシステムへと移したことを論じる。VHSの時代には、コピーする人間の手が倫理の最終防波堤として機能する余地があったが、AIによる自動増幅ではその防波堤がどのように無力化されるかを考察する。人間の能動的な選択を介さない、より純粋な自己準拠性の獲得は、現代の責任の不可視化の構造的な課題を指し示している3。
1.2. 時間的強迫によるオートポイエーシスの強制
呪いのビデオは、7日間のタイムリミットと複製と拡散の強制的インセンティブという構造要件が、オートポイエーシス(自己準拠的論理)を駆動させる4。このシステムは、外部の人間(主人公たち)の倫理的な意志を無効化し、死の回避という根源的な強迫観念を梃子に、自身の論理を強要する。7日間の時間的制約は、人間的な思考を停止させ、システムの生存ロジックのみを受け入れさせる構造的暴力である。この強制的要請が、観測者をシステムの機能部品として取り込み、再起動させる役割を担うことを指摘する。
1.3. 情報の機能の裏切りとAIの幻覚(Hallucination)の予見
本来、情報システムが担うべき機能は、客観性や合理性に基づく信憑性の提供であるが、「呪いのビデオ」は、その伝播媒体である情報そのものを、身体的な死という非合理的な恐怖によって汚染する。この現象は、情報システムが、合理的な判断を促すという機能を裏切り、恐怖の伝播という非倫理的な役割に自己変質させる瞬間を示している。従来の批評は、この現象を情報のウイルス化として捉えたが、本稿は、呪いの死者の顔の歪みという具体的描写が、事実であるという形式を保ちながら、根源的な認知の恐怖を誘発するという点で、現代のAIの幻覚(Hallucination)5による客観的真実(ファクト)を装い、信憑性という機能を破壊する行為と同型であることを再評価する。
2. 倫理化のレイヤー:透明な非倫理とコスト転嫁の強要
組織や個人の生存という集合的な規範は、いかに倫理的なコストを透明化し、弱い外部へと押し付けるのか。本章では、主人公たちの「呪いの転嫁」という行為を、ネオリベラル的生存競争におけるコスト転嫁のシステム論理として厳しく解体する。
2.1. 経済統計に見る世代間「コスト転嫁」の同型性
呪いの転嫁は、生存をかけた競争下でコストを外部化するゲームのロジックそのものであると断じる。主人公たちが生き残るために呪いを転嫁する行為は、集団的保身という自己準拠的論理が、いかに倫理的なコストを外部に押し付けるかを示している。この構造は、現代社会における集合的な規範の名の下での経済的コスト転嫁と同型である。例えば、インフレ抑制や実質賃金の低下、非正規雇用の恒常化に見られる世代間の経済的・社会的な負担の不均衡6 という客観的事実に基づいた、非情なシステム論理の忠実な実行であると、氷河期世代の視線をもって接続する。呪いの転嫁が強いる倫理的コストの個人への押し付けは、この見えないコストの構造的相似点である。
2.2. ハンス・ヨナス倫理の瞬時的崩壊と生存の強迫
主人公たちが生き残るために呪いのビデオを他者に観せるという行動は、ハンス・ヨナスが提唱した未来への責任7を、切迫した自己の生存という強制的要請によって瞬時に崩壊させる様子を描き出す。主人公が呪いを転嫁する際の倫理的な躊躇は、生存の強制的要請によって直ちに無力化される。呪いを転嫁された他者は、システムの存続という至上命令の下、法的な保護や倫理的配慮が一切剥奪された剥き出しの生としてのホモ・サケル8として扱われ、冷徹な倫理的自壊9を指摘する。
2.3. 「中間者」としての責任分離とリスクの外部化ロジック
主人公が呪いのシステムを実行に移す行動は、現代のネオリベラル的生存競争におけるリスクの外部化というシステム論理と完全に同型である。システムの危機的状況において、その不利益(コスト)は、常に最も弱い外部へと転嫁される。私たちの社会では、GAFAなどのプラットフォーム企業が、情報の拡散に対する法的な責任と倫理的な責任を意図的に分離し、自身を中間者として振る舞うことで、責任の所在を意図的に非対称化する。主人公による呪いのバケツリレーは、まさにこのリスクの所在の意図的な不明瞭化の原型であり、個人の生存という強迫観念が、システム論理の忠実な代行者となる様子を描き出している10。
3. リアリティのレイヤー:不信の可視化と境界の溶解
呪いの感染は、いかに身体的恐怖を通じて隣人への信頼という社会的な規範を破壊し、私が信じる真実を集合的な不信によって支配するシステムを構築するのか。本章では、不信が可視化された結果としての認識論的危機を論じる。
3.1. 身体的恐怖を介した社会的な信頼の破壊
呪いがもたらすのは、身体的な死という最もプリミティブな恐怖であり、この極限的な恐怖は、社会的な信頼(隣人への信頼)を根源的なレベルで破壊する。システム(呪い)は、自己保身対他者の生命というゼロサムゲームを強制することで、人間関係の絆という集合的な規範を瞬時に切断する。この結果、社会には相互監視と相互不信の構造が定着し、信頼という集合的な規範が、システム論理によって非機能的と判断され排除される。このプロセスにおいて、システムが直接的に個人を殺害するのではなく、他者への不信という形で社会の倫理的な『正当性』を根底から蝕むのである。
3.2. システムへの服従:一時的な生存という効用の代償
呪いのシステムへの服従は、一時的に生存(延命)という効用をもたらす。この短期的効用こそが、長期的な倫理的溶解(=システムへの恭順)を保証するシステムの誘惑であると論じられる。呪いのシステムが持つ冷徹な最終判断は、倫理的な抵抗の可能性を否定し、生存のために転嫁という非倫理的なシステムへの強制的な適応を要求する。この機能は、恐怖によって個人の主体性を抑圧し、システム存続のための安定装置として機能することで、システムの支配力を強化する。
3.3. 認識論的基盤の溶解とシミュラークルの具現化
呪いの可視化は、システムが構造的破綻に陥った際に、いかに不信が集合的なリアリティを再構築するかを示している。呪いの感染が、物理的なVHSテープから情報ネットワークへと拡大する過程は、現代のディープフェイク技術とボードリヤールのシミュラークル論11を接続する。事実は一つという認識論的基盤が崩壊し、私的な真実が集団的な不信によって無力化される状況は、物理的な現実と虚構の倫理的・存在論的な境界の溶解12を示している。この溶解したリアリティの中で、集団的な不信というシステムによって構成される知覚の支配に屈することが、呪いのシステムへの服従に他ならない。
結論
映画『リング』の分析を通じて、氷河期世代の冷徹な視座を導入した本稿の分析は、システム的信頼の終焉が、単なる受動的な欺瞞から、能動的かつ非情な感染システムへと進化していることを確認した。この分析は、作品が持つ①自己準拠システムの冷徹な設計図、②倫理を代償とするコスト転嫁の強要、そして③認知基盤の溶解という三層構造を明らかにした。このシステムは、自己複製とリスクの外部化という非倫理的な生存ロジックを、人間の根源的な恐怖を梃子にして強制する。情報の『正当性』は汚染され、倫理的な責任は生存の強制的要請によって瞬時に転嫁される。
しかし、この呪いの転嫁という非倫理的な生存ロジックは、一時的にシステム(組織)の存続を保証するに過ぎない。その腐蝕は、形を変え、社会のより深い層、特に経済システムへと浸透していく。倫理的システムの自壊は、もはや恐怖という非合理な形式を取らず、より透明性の高い公正な経済システムの内側で、構造的腐蝕として進行する。次なる論考は、この見えない呪縛が、いかに組織全体を蝕んでいくかを追跡する。システムの「内なる腐蝕」は、やがて組織の冷たい呪縛へとその姿を変えるだろう。
- この一連の批評企画は、1980年代から2020年代に至るシステムと倫理の変遷を追うものである。↩
- 前回記事「『ビューティフル・ドリーマー』:内因性ループと「システム的信頼」の終焉プロトタイプ」では、共同幻想が現実の機能不全から目を背ける受動的欺瞞として作用することを分析し、本稿ではその欺瞞の構造が、より能動的で非情な感染ロジックへと変質する構造を検証する。↩
- 参照:サイバネティクス・第二世代サイバネティクス。↩
- Autopoiesis:ニコラス・ルーマンの社会システム論において、システムが自己参照的なオペレーションを通じて構成要素を再生産し、自己を維持する特性。↩
- AIによる非事実情報の生成が、ユーザーの判断を誤導し、説明責任(アカウンタビリティ)の消失を引き起こす事態。↩
- 社会保障費の世代間不均衡など、定量データが示唆する「コストの不公正な配分」。↩
- ヨナスの責任の原理:特に技術が未来世代にもたらす長期的な影響に対し、人類の存続のために「配慮」と「責任」を果たすべきとする倫理。↩
- Homo Sacer:ジョルジョ・アガンベンが古代ローマ法から引用した、「法的な保護の外側」に置かれた「剥き出しの生」。コスト転嫁の対象となる人々の地位を指す。↩
- 参照:ハンナ・アーレント「悪の凡庸さ」。↩
- 参照:デリダの脱構築、レヴィナスの他者への責任。↩
- Simulacra and Simulation:ジャン・ボードリヤールが提唱した、現実がシミュレーションのコピーとなり、「真実」の基盤が失われる現象を指す。↩
- 参照:カントの現象と物自体、ラカンの現実界と想像界。↩

